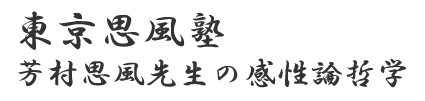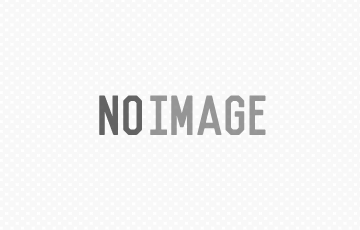感性論哲学の役割


芳村思風一語一会 vol.5635
感性論哲学の役割
感性論哲学は、芳村思風の個人の哲学ではない。
感性論哲学は、感性をベースにしたことで、
観念論と唯物論という相対する2つの哲学の対立を乗り越えて統合した。
感性論哲学は、近代・西洋の「人間の本質は理性である」という時代から、
次の新しい時代・東洋の時代の「人間の本質は心である」
という新しい時代を作る哲学である。
感性論哲学が、個人の哲学を越えた理由は、
感性論哲学が宇宙の摂理に則った哲学だからである。
宇宙の摂理とは、科学でいうと宇宙の法則のこと。
人間は、宇宙の摂理によって生み出された。
だから人間は宇宙の一部であり、
人間も宇宙そのものと言える。
人間が人間らしく生きるとは、
「宇宙の摂理」にのっとって生きるということ。
人間は寝ていても死なないのは、
命が人間の力で生きているのではなく、
命を作った摂理の力によって生かされているから。
宇宙の摂理とは、プラスとマイナスに評価される相反するエネルギーが、
対立することなく協力して働いて、秩序を保つ働きのこと。
2極の対立から、競争することで成長する時代は終わった
戦って勝つことが正しい時代が終わったのである
人間が人間らしく生きるとは、矛盾を生きるということであり、
また不完全を生きるということであり、
矛盾を活かし、不完全を生きるという生き方である。
「宇宙の摂理」にあった生き方とは、常に対立するものを、
対立させないで協力しあって働くという生き方。
国の違い、考え方の違い、宗教の違いで対立する時代は終わったのである。
これからの1000年は感性の時代
感性の時代の考え方が「感性論哲学」
芳村 思風
やさしい笑顔と光がすべての方に届きますように・・・
※新刊 2025年1月発売
「ほんとうの自分が見える55の問い」
文芸社

Source: 芳村思風 感性論哲学の世界