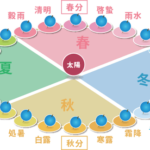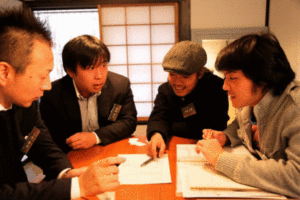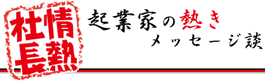今年最後になります
禅の知恵と古典に学ぶ人間学勉強会
[metaslider id=”28292″]今年1年の中で、書籍出版が続いた年で
言志四録と禅の人間学


1年の講義を振り返ると
10月:無着禅師
中国の唐時代後半に活躍された無着(むちゃく)禅師という方がおられました。この方は、仰山(ぎょうざん)禅師という大禅匠の法を嗣(つ)いだ方ですが、若い頃に五代山に行脚(あんぎゃ)したことがありました。五台山は、文殊菩薩を祀る霊場として古来有名な所です。求道心に燃えていた無着青年は、五台山のお寺に宿泊した際に、夢の中で文殊菩薩と出会い、教えを受けることができました。
9月:碧巌録から百丈和尚の話
百丈懐海(ひゃくじょう・えかい。七四九~八一四)禅師は、唐の時代の福建省長楽の生まれ、二〇歳で西山慧照和尚のもとで出家し、南嶽の法朝律師から具足戒を受け、広く仏教を学び、馬祖大師の法を嗣いだ。
8月:禅僧に学ぶから漢詩「円通寺」より良寛さんについて(江戸時代後期を代表する優れた禅僧)
「散る桜 残る桜も 散る桜」
という有名な辞世の句を残された方でもあります。
「今どんなに美しく綺麗に咲いている桜でもいつかは必ず散る。そのことを心得ておくこと。」
桜は散る。
命は散る。
必ず散りゆくこの命とは何なのか。
人がその人生において本当に考え抜くべき問いを残してこの世を去った良寛の辞世の句
いかに生きるかについてはよく聞くこともあり取り上げられるテーマとしても多いと思いますが
いかに死ぬか?
はなかなか無いと思われます。禅においては「生を明らめ死を明らむるは、仏家一大事の因縁なり」
(生きること、死ぬことの意義を明らかにするのが、仏法を学ぶ者にとって最も大切な問題である)
という道元禅師の言葉があります。また、唐時代には、型にはまった禅問答よりも、その場その場で活き活きとしたやり取りをすることが尊ばれました。
東アジア(中国、朝鮮、日本)における最大の古典である「論語」の精神は、徳治(とくち)主義といわれます。徳のある立派な人物が、正しい理念と思いやりの心をもって人を治めていくという考え方です。
徳治の中身には、いろいろな面がありますが、どのような人にも寿命があるように、要職にある人にも、引退の時期が来ます。そのときの出処進退、特に退く時に潔くきれいに退くということが大切ですが、同時に難しくもあるとされます。
佐藤正忠著 (経済界、1991年1月刊)
『わが戦後財界秘史〈1〉身命(いのち)、果てるとも』 P.134~151より野村證券中興の祖と言われる奥村綱雄氏に関する章ですが、
特に、P.143「持つべきは三人のブレーン」の章に、
大徳寺住職・立花大亀(だいき)老師との印象深いエピソードが記載されています。
「日本の論語」「人生訓の名著」「指導者(リーダー)のための教科書」と言われる『言志四録(げんし-しろく)』は、江戸時代末期の儒学者、佐藤一斎(さとういっさい)が著した随想録・語録です。
特に印象的だった、生死についてと言志四録について
生死について
禅においては「生を明らめ死を明らむるは、仏家一大事の因縁なり」
(生きること、死ぬことの意義を明らかにするのが、仏法を学ぶ者にとって最も大切な問題である)
という道元禅師の言葉があります。また、唐時代には、型にはまった禅問答よりも、その場その場で活き活きとしたやり取りをすることが尊ばれました。
参加者の方からはちょうどオウム事件の死刑執行が最近あり、ちょうどそれを考えていた際、何故彼らはそこに走ってしまったのか?それは今は反省してもその時はそれが答えになっていた。その答えを示したのが麻原だったのではないか。だから今を生きる事が出来ずに、他の人の中に生きる、依存するというのが答えを示してくれる人に依存してしまう環境があったのではないかと。
また、今、ここ、自己の禅の教えの中において一番実践しているのは子供(赤ちゃん)
先々を考えず、今!を素直に生きている。先々の悩みを持たず邪念もない。
だから子供心、童心に戻るという意味はそういうところにあるのかなと思います。
古巣社会起業大学において田坂先生のお話の中で
リーダーが持つべき大切な覚悟は「死生観」
特に経営者、政治家、リーダーに必要
↓
経営者であれば部下、社員の人生を預かる。それは1人でも100人でも!
政治家であれば地域の方々、時に国民
自分が命に対する深い眼差しを持っていなければリーダーになるべきではない。そしてジョブズの言葉を参考に「今日が最後の日だと生きてきたらいつかそれが真実の日になる」
そこに至るには、苦労、困難、挫折、敗北あらゆる困難の中でこそ成長するのがリーダーであり、乗り越えられるからこそリーダーになれる。
言志四録
言志四録についての紹介
「日本の論語」「人生訓の名著」「指導者(リーダー)のための教科書」と言われる『言志四録(げんし-しろく)』は、江戸時代末期の儒学者、佐藤一斎(さとういっさい)が著した随想録・語録です。
佐藤一斎は、42歳で筆を執った『言志録(げんしろく)』を皮切りに、『言志後録(げんし-こうろく)』『言志晩録(げんし-ばんろく)』を著し、最終作となる『言志耋録(げんし-てつろく)』を書き上げたのは82歳のときでした。
内容は学問修養の心得、倫理道徳の規範から、指導者論、そして処世の教訓、身体の養生法まで多岐にわたっています。
全体で1133条ありますが、明治維新を導いた薩摩藩の西郷隆盛は、『言志四録』を座右に置き愛読書としていました。さらに、その中から101条を撰び、修養の資(もと)として暗誦するほど読みこみました。
一斎先生の門に学んだ人々は数千人になるといわれますが、その中でも有名な人物は、山田方谷(やまだ-ほうこく)、佐久間象山(さくま-ぞうざん)、安積艮斎(あさか-ごんさい)、大橋訥庵(おおはし-とつあん)、横井小楠(よこい-しょうなん)など、幕末を代表する学者や思想家がいます。
、幕末期に財政破綻寸前の備中松山藩5万石を立て直した名財政家であり、卓越した政治家である。わずか8年間の改革で借金10万両(現在の価値で約300億円)を返済し、余剰金10万両を作った。
明治に入ってからは、薩長閥の重鎮で元勲の大久保利通、木戸孝允などから新政府の要職への就任要請があったが、方谷は固辞。根本思想は「武士も農民も慈しみ愛情をもって育て、藩士・領民全体を物心ともに幸福にする」「領民を富ませることが国を富ませ活力を生む」という「士民撫育」の考え方
そして、彼の物事に向かう基本姿勢は「至誠惻怛(しせいそくだつ)」である。「真心(至誠)と悼み悲しむ心(惻怛)」を人間としての正しい道、最高の行動規範とした。
、60歳で江戸幕府直轄の最高学府「昌平坂学問所」の教授を務め、ペリー来航時のアメリカ国書翻訳や、プチャーチンが持参したロシア国書の翻訳及び返書起草に携わるなど、幕末の政治・外交を支えました。艮斎が学び教えていた朱子学は江戸幕府の正学とされており、江戸幕府が国を治めるために利用されていました。ですが、師であった佐藤一斎の影響を受けたのでしょう。艮斎は、朱子学だけではなく、危険視されていた陽明学など他の学問や宗教も摂取した新しい思想を唱えます。また、外国事情にも詳しく、海防論の論客としても知られました。
艮斎の教え子たちは、幕末・維新という日本の大変革期において、中央や地方で指導的な役割を果たし、近代国家日本建設の人材となりました。艮斎の塾は、著名な門人が200人も綺羅星の如く輩出した、日本史上有数の学塾です。
江戸末期の儒学者。江戸の人。日本橋の豪商大橋家の養子。佐藤一斎に学び、朱子学を唱えて、攘夷(じょうい)を主張した。老中安藤信正襲撃を計画して投獄され、獄死。著「闢邪小言(へきじゃしょうげん)」「元寇紀略(げんこうきりゃく)」など。
大橋訥庵の目標、戦略は、「大日本国を蛮夷にならせじと申す所に大活眼を着けたまわねば恢復の成功を得たまうべからず」。
すなわち「日本を蛮夷(野蛮な外国)にしないことが王政復古を成功させる」ことと言っております。
幕末の熊本藩士・政治家・思想家。肥後生。名は時存、字は子操、通称平四郎、別号に沼山。江戸に遊学して藤田東湖らと交わる。藩校時習館の守旧的な学風を批判、元田永孚らと実学党をつくり、私塾小楠堂で子弟を教育する。のち福井藩主松平慶永(春獄)に招かれて藩の政治顧問となり藩政改革を指導
「実際に役立つ学問こそ、最も大事」という小楠の教えを受けた人たちのグループを「実学党」と言います。当時の熊本(肥後藩)には、実学党に対して、保守的な「学校党」とか、尊皇攘夷をめざす「勤王党」などのグループがあり、幕末から明治にかけて、政争を繰り返していました。
文久2年(1862)、幕政改革のため、次のような「国是7カ条」というものをまとめています。
国是7カ条
- 大将軍上洛して、烈世の無礼を謝せ(将軍は自ら京にいって、天皇へ過去の無礼を謝る)
- 諸侯の参勤を止め、述職とせよ(参勤交代制度の廃止)
- 諸侯の室家を帰せ(大名の妻子を国元に帰す)
- 外様譜代に限らず、賢を選んで政官となせ(優れた考えの人を幕府の役人に選ぶ)
- 大いに言路を開き、天下公共の政をなせ(多くの人の意見を出し合い、公の政治を行う)
- 海軍を興し、兵威を強くせよ(海軍をつくり軍の力を強くする)
- 相対貿易を止め、官の交易となせ(貿易は幕府が統括する)
勝海舟曰く「おれは今までに天下で恐ろしいものを二人見た。横井小楠と西郷南洲だ」。日本史の教科書でもろくに取り上げられず、幕末もののドラマで登場することもほとんどない。しかし小楠こそ、坂本龍馬や西郷隆盛をはじめ、幕末維新の英傑たちに絶大な影響を与えた「陰の指南役」であった。
このうち、幕末日本の先覚者といわれる象山(ぞうざん)の門下から、勝海舟(かつ-かいしゅう)、坂本竜馬、吉田松陰(しょういん)、小林虎三郎などの幕末の日本を動かした志士が輩出しました。
また、吉田松陰の門下からは高杉晋作、久坂玄瑞(くさかげんずい)、木戸孝允(きどたかよし)、伊藤博文、山県有朋(やまがたありとも)などが輩出して、輝かしい明治維新を形成することとなります。
生前に次々と刊行された『言志四録』によって、一斎と直接面識のない幕末の志士にも大きな精神的影響を与えたのです。
なかでも、西郷隆盛は、『言志四録』をほとんど暗誦するまで繰り返し熟読してその中から101の言葉を選び出したのでした。こうして『西郷南洲(なんしゅう)手抄(しゅしょう)言志録』が生まれたのです。佐藤一斎の教えは、『言志四録』によって、ことに西郷隆盛によって、明治維新の精神的支柱となったと言えます。
「言志四録」「言志四録」は、佐藤一斎の人格と学問が結集した名著で、40年をかけて書きつづられた随想録です。
一斎の生前に『言志録』、『言志後録』、『言志晩録』、『言志耋(てつ)録』の4書として出版されました。その総称を「言志四録」といいます。比較的短い箴言(しんげん)の集まりですが、記載されたものは全体で1133条にもなります。西郷隆盛は、その中から101条を抄録して、繰り返し味読しました。
(1)天につかえる心
凡(およ)そ事を作(な)すには、
須(すべか)らく天に事(つか)うるの心(こころ)有るを要すべし。
人に示すの念(ねん)有るを要せず。
(言志録・第3条)(現代語訳)
すべて事業や行動を起こすには、天(大自然・神・仏)に生かされていることを考え、それに感謝し、敬(うやま)う気持ちを忘れてはならない。他人に誇り、認めてもらおうとする気持ち(私心)があってはならない。
この言葉は『言志四録』の中でもとても有名な章で、私たちが日常生活の中でつい忘れがちな真理を教えてくれています。
「天に事(つか)うる」とは、天を敬して己を尽くして誠実に生きることです。佐藤一斎は、上記の言葉をさらに短く、「尽己(じんこ:己を尽くす)」という二文字にして、弟子の山田方谷に書いて贈ったと伝わっています。
自分をあざむかずに、誠実に物事に取り組むことによって、はじめて人間が真実となり、自分が関わるところの一隅を照らすことができるようになります。一隅を照らす人間になれることが、この世に生きる私たちにとって最も肝要なことであり、他人の評価を気にする必要はないと
一斎は教えています。
『修身教授録』で有名な森信三先生は、つぎのように開設されています。
<森信三先生の解説:『西郷南洲の遺訓に学ぶ』より>
p.127 相対をすてて絶対に帰する
この節は甚(はなは)だ簡明ではありますが、しかし翁の根本信念を示すにおいて、おそらくは、最も根本的な節と申すべきでありましょう。すべてはこれだけに尽きていると申してもよいのであります。
「人を相手にせず、天を相手にせよ」これすなわち相対(そうたい)をすてて絶対(ぜったい)に帰するということでありましょう。
人というものは、我と相対立するもので五分五分のものであります。かく相対的な五分五分の関係では、向うが変わればこちらも変わるのである。すなわち動揺(どうよう)恒(つね)なきものであります。向うが強ければこちらが引き摺(ず)られ操られる、これが相対的関係というものであります。
それから脱して天を相手にする、すなわち絶対を相手にして絶対に帰し、絶対に自己をささげる。そこではじめて相対的なる人情の離反(りはん)合不合ということによって一々自己が動かされることがなくなるのであります。
天を相手にすることによって、始めて人は己れを尽して人を咎(とが)めず、つねに自己の誠の足らざるを尋ねるという処にも到るのである。天を相手にすれば、己れを尽すということは自然に出来るのであります。(中略)
人を相手にしていると、人の態度が一々問題になります。人をはなれて、天を相手にすれば、人の事は第二義、第三義になって、成程(なるほど)よい方がよいには違いないが、しかし仮りによくしてくれなくても、それが第一義的な関心事とはならなくなるのであります。
道理からすれば「天を相手にせよ」とただそれだけでよい。天を相手にすれば、それ以下のことは自らにして出来るわけであります。
そこで又、「己れを尽(つく)して人を咎(とが)めず、わが真の足らざるを尋ねる」ということは、天を相手にするという態度を一歩一歩徹して行く。すなわち工夫の一歩一歩という意味を持つのであります。
一燈の明るさを頼りに進む
一燈(いっとう)を提(ひっさ)げて、暗夜(あんや)を行く。
暗夜を憂(うれ)うる勿(なか)れ、只(ただ)一燈を頼(たの)め。
(言志晩録・第13条)
(現代語訳)
暗い夜道をひとつの提灯(ちょうちん)をさげて行くとき、闇夜の暗さを心配するのではなく、ただ提灯の明るさを頼って行けばよい。
(後ろを向いて不安がるのではなく、前を向いて進め)
「言志四録」の中でも最も有名な言葉の一つです。ここでいう「一燈」とは、すべての人の心の中にある霊的な光(心の力)のことです。禅宗では仏心といいます。人が前向きに進もうとするとき、心の光は、意志となり、知恵となって、行く先を照らしてくれるということを佐藤一斎は述べています。
逆にいえば、心が光を失って暗く沈むとき、たとえ行く先に明かりがあっても、その明かりを見失って、暗闇にさ迷うことになるとも言えます。そうならないために、日ごろから古典を学び、心を磨いて行く必要があるのではないでしょうか。